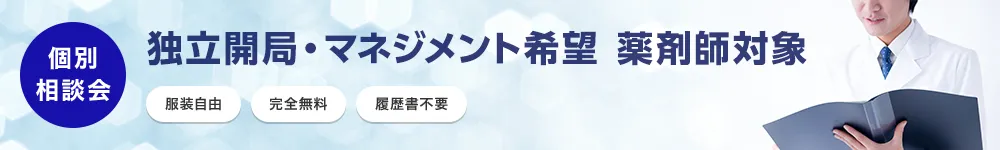調剤薬局の経営は厳しい?業界動向や将来性・今後の生き残り戦略とは
近年、調剤薬局の経営環境は厳しさを増しています。その原因としては、医療費削減政策の影響で薬価の引き下げが続いているほか、調剤併設型ドラッグストアの拡大や大手企業による処方箋受取サービスの台頭などが挙げられます。また、後継者不足・事業承継の問題も深刻化している状況です。
しかし、厳しい局面を迎える中でも、調剤薬局には将来性があります。当記事では、調剤薬局の現状と経営が厳しい理由や、調剤薬局の厳しい経営を乗り越える方法について解説します。
1.調剤薬局の経営は厳しい?
近年、調剤薬局の経営は厳しい状況にあります。東京商工リサーチの調査によれば、2024年1~7月の調剤薬局の倒産数は累計22件で、前年同期比266.6%の増となっています。
出典:東京商工リサーチ「2024年1-7月「調剤薬局」倒産 過去最多22件 大手再編と新規参入で、中小の「調剤薬局」は冬の時代へ」
また、2024年において調剤薬局を含む医薬品小売業者の倒産数は11月までに34件と、過去10年で最多を記録しました。負債総額は約144億円にのぼり、年間では37件前後に達する見通しです。
2.業界動向から見る!調剤薬局の経営が厳しい理由
倒産以外に、廃業や他社への事業譲渡(M&A)も増えています。薬局数自体は増加している一方で、高齢の経営者が後継ぎ不在で自主廃業を選ぶケースも少なくありません。
調剤薬局の経営が厳しいと言われるのにはさまざまな理由が考えられますが、業界動向の変化に目を向けると、主に次の4つの要因が挙げられます。
2-1.医療費の削減が推進されている
日本では国民皆保険制度を維持するため、国主導で医療費削減の政策が進められており、その一環として調剤報酬の改定や薬価引き下げが行われています。
調剤報酬は、改定のたびに減額傾向にあります。また薬価についても、ジェネリック医薬品の普及促進や市場実勢価格を反映した引き下げにより、薬局が得られる薬価差益(仕入れ価格と薬価の差による利益)は縮小傾向です。また、2025年度も薬価の引き下げが検討されています。
2-2.調剤併設型ドラッグストアが増えている
ドラッグストア業界が好調な伸びを見せる中で、調剤薬局を併設したドラッグストアが急増しています。大手チェーンドラッグストア各社は処方箋受付が可能な店舗を積極的に展開しており、調剤専門薬局とドラッグストアの垣根は崩れつつあるのが現状です。
調剤併設型ドラッグストアには「広い店内でOTCや日用品もまとめて買える」「夜遅くまで営業している」という強みがあります。その利便性の高さに惹かれた患者さんが調剤併設型ドラッグストアを利用することで、従来の門前薬局や街の薬局は顧客流出による売上減少に直面しています。
2-3.大手企業の処方箋受取サービスが拡大している
IT企業やコンビニエンスストアなど、異業種の大手企業では従来の薬局以外で処方薬を受け取れるサービスを次々に展開しています。たとえば、ファミリーマートは2022年に東京都内約2,400店舗で「ファミマシー」というサービスを開始しており、処方薬をコンビニで24時間いつでも受け取れるようになりました。
セブンイレブンでは、店内に処方箋受付機と薬受取ロッカーを設置する試みも始まっています。山形県酒田市のセブンイレブン14店舗では、2024年に処方箋受付機と受取ロッカーの設置が行われ、処方薬の受け渡しがより身近に行えるようになりました。さらに、オンライン診療・服薬指導の普及に伴い、処方薬の宅配サービスや当日配送を実施する企業も登場しています。
2-4.後継者不足が深刻化している
地方を中心に薬局オーナーの高齢化と後継者不足は深刻な問題となっています。帝国データバンクの調査によると、2024年における調剤薬局を含む医療業の後継者不在率は61.8%です。
出典:株式会社 帝国データバンク「全国「後継者不在率」動向調査(2024年)」
多くの薬局オーナーが引退適齢期を迎えているにもかかわらず、自分の子や社員などの次世代に経営を引き継ぐ体制が整っていないのが現状です。その結果、黒字経営でも高齢により廃業を選ぶケースや、やむなく薬局を売却・譲渡する事例が増えています。
後継者不在の薬局では、有能な薬剤師スタッフがいても事業継続が難しく、地域のかかりつけ薬局機能が失われる恐れがあります。都市部においては薬剤師確保が難しくなっており、小規模薬局では人手不足が原因で営業時間短縮やサービス低下に陥る例も挙げられます。
3.調剤薬局経営の将来性は?
厳しい状況が続く調剤薬局業界ですが、調剤薬局には依然として地域医療インフラとしての重要な役割が期待されています。その1つが2021年8月に創設された、調剤薬局の機能強化を図る新たな認定制度である「地域連携薬局」や「専門医療機関連携薬局」です。
地域連携薬局とは、在宅医療や24時間対応、服薬管理など、地域の医療機関や他薬局と連携しつつ患者さんを支える中核的役割が期待される薬局を指します。専門医療機関連携薬局は、がん治療薬など専門的な薬剤提供体制や高度な薬学管理ができる薬局です。いずれも従来の「かかりつけ機能」を明確化・強化する目的で導入されたもので、認定を受けた薬局は看板などにその旨を表示できます。
また、これまで調剤薬局の薬剤師は調剤などの対物業務が中心でしたが、現在は服薬管理・指導などの対人業務に重きを置くようシフトしています。高齢化が進む中、患者さん一人ひとりに合わせた薬物治療のマネジメントや健康サポートへのニーズは高まっています。カウンセリングや医療機関との連携など、調剤薬局ならではの役割を担っていることから、経営は厳しくとも将来性は明るいと言えるでしょう。
4.調剤薬局の厳しい経営を乗り越える方法
調剤薬局の将来性は明るいものの、厳しい経営を乗り越えて成功させるためには、時代の変化に対応する必要があります。以下では、経営者として調剤薬局を存続・発展させるための具体的な対策を3つ紹介します。
4-1.医薬品の購入費・人件費の削減を図る
まず取り組むべきは、経費の見直しによる収支改善です。調剤薬局の支出構造では、一般的に最も大きな割合を占めるのが医薬品の仕入れ費用で、その次に人件費となります。この2つのコストを適正化できれば、利益率を確保しやすくなるでしょう。
医薬品の購入費削減については、仕入先である医薬品卸との価格交渉や発注方法の工夫などが挙げられます。複数の卸業者と取引して相見積もりを取ったり、近隣薬局同士で共同購入の枠組みに参加したりしてスケールメリットを出す方法が有効です。
ただし、人件費を削減しようと単純にスタッフ数を減らすのは現場に負担がかかり逆効果です。重要なのは人件費の最適化であり、業務内容を洗い出して適材適所に配置することが先決です。たとえば、ピッキングや薬袋への薬剤セット、在庫数のチェックなど、薬剤師でなくても対応可能な業務は、調剤事務や助手に任せる方法が挙げられます。そうすることで薬剤師は処方監査や服薬指導など本来の業務に専念でき、少人数でも円滑に業務を遂行できるでしょう。
4-2.かかりつけ薬局を目指す
かかりつけ薬局とは、患者さんが「何かあればまず相談したい」と思える身近な薬局・薬剤師がいる薬局のことです。調剤薬局の経営を安定させるには、地域住民から信頼され、選ばれる薬局になる必要があります。
「この地域にはこの薬局が必要だ」と思ってもらえる存在になるには、患者さん本位のサービス提供が欠かせません。単なる「薬の受け渡し所」ではなく、患者さん一人ひとりに寄り添うかかりつけ薬局となれば、これからの時代も生き残れる可能性が高くなるでしょう。
4-3.薬局DXを推進する
厳しい経営を乗り越えるためには、デジタル技術を活用した薬局DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進も欠かせません。薬局DXの具体例には、電子薬歴システムの導入、電子処方箋への対応、オンライン服薬指導の活用、在庫管理・発注のデジタル化などが挙げられます。
DX化には初期投資が必要ですが、中長期的に見れば投資効果の高い経営改善策になると言えます。特に若い世代の患者さんはデジタルサービスへの抵抗が少ないため、DX対応が集客面でのアピールにもなります。ITの力で業務効率化を図り、サービスの質向上を目指しましょう。
まとめ
医療費削減策による収益圧迫、ドラッグストアとの競争激化など、さまざまな要因が絡んで調剤薬局の経営は厳しさを増しています。後継者不在により、廃業や事業売却を選ぶケースも少なくありません。
調剤薬局が厳しい時代を生き抜くには、地域に根差して患者さんに寄り添う「かかりつけ薬局」の役割を担うことが求められます。薬局DXにより業務効率化やコスト削減を図るなど、従来のやり方に固執せず時代の変化に柔軟に対応することも大切です。
ユニヴでは、調剤薬局業界の動向も踏まえた上で、独立・開業したい薬剤師の方をサポートしております。具体的なことは決まっていなくても、お気軽にご相談ください。