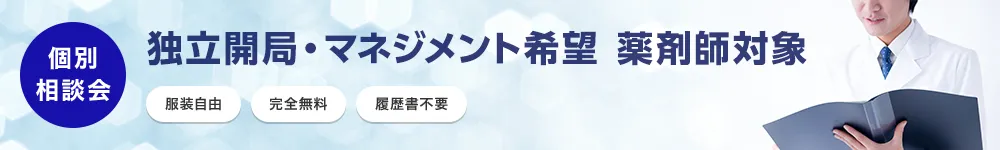調剤薬局を経営すると儲かる?業界の課題や経営の成功ポイントを解説
調剤薬局の経営に成功して儲けるには、経営状況を左右する多くの要素を理解する必要があります。薬価改定や人材不足、大手チェーンの進出など、薬局を取り巻く環境は変化が続いており、従来のやり方だけでは利益を確保しづらい状況です。一方で、在宅医療への対応や健康サポート薬局としての機能強化など、新たな取り組みによって経営を安定・拡大させる余地も十分にあると言えます。
この記事では、調剤薬局経営者の年収や、調剤薬局経営にかかわる課題、経営を成功させるためのポイントについて紹介します。
1.調剤薬局の経営は儲かる?
調剤薬局の経営が儲かるかどうかは店舗の立地や規模、応需する処方箋の枚数など条件によって異なるため、一概には言えません。
参考として、厚生労働省の第24回医療経済実態調査(医療機関等調査)では、保険調剤業務を行う「保険薬局」の平均的な税引前利益は下記の通りとなっていました。
| 個人薬局 | 約792.3万円 |
|---|---|
| 法人薬局 | 約1,556.3万円 |
出典:厚生労働省「第24回医療経済実態調査 (医療機関等調査) 報告 - 令和5年 実施」
以下では薬剤師と薬局経営者の平均年収を比較して、薬剤師として薬局などに勤務した場合よりも、調剤薬局を経営したほうが儲かるかを解説します。
1-1.薬剤師の平均年収
令和5年賃金構造基本統計調査によると、薬剤師の平均年収は約578万円でした。
なお、薬剤師の平均年収は本人の年齢や職位などによって変化します。参考として薬剤師の平均年収を年齢別に区分すると下記の表の通りです。
| 年齢 | 平均年収 |
|---|---|
| ~ 19歳 | 約350万円 |
| 20~24歳 | 約471万円 |
| 25~29歳 | 約554万円 |
| 30~34歳 | 約648万円 |
| 35~39歳 | 約624万円 |
| 40~44歳 | 約613万円 |
| 45~49歳 | 約690万円 |
| 50~54歳 | 約724万円 |
| 55~59歳 | 約571万円 |
| 60~64歳 | 約604万円 |
| 65~69歳 | 約493万円 |
| 70歳~ | 約451万円 |
年齢別での平均年収が最も高くなるのは50~54歳の「約724万円」です。実際に得られる年収は個人差があるものの、個人薬局の平均的な利益である「約792.3万円」に近い金額であると言えます。
ただし薬剤師の平均年収には、薬局を経営する薬剤師の年収も含まれている点に注意してください。
また、薬剤師の平均年収は年齢の違いで大きな幅があり、薬局経営の利益に近い年収を常に得られるわけではありません。
1-2.薬局経営者の平均年収
薬局経営者の年収は、経営する薬局において処方箋をどの程度応需できるかで変わります。1日あたり30~40枚の処方箋を応需する薬局は年収500万~600万円、1日あたり50枚の応需する薬局であれば年収600万~800万円が年収相場となるでしょう。
参考として厚生労働省の第24回医療経済実態調査(医療機関等調査)によると、1店舗を開業している管理薬剤師の平均年収は約933万円でした。
出典:厚生労働省「第24回医療経済実態調査 (医療機関等調査) 報告 - 令和5年 実施」
複数の店舗経営を行った場合にどの程度儲かるかは分からないものの、規模が大きくなれば複数の医療機関から処方箋を応需できます。調剤技術料の点数も高くなり、年収1,000万円以上を目指すことも不可能ではありません。
2.そもそも薬局とは
そもそも薬局とは、薬剤師が医薬品販売や調剤、医薬品に関する情報提供・指導などを行う施設のことです。
薬局は大きく分けて「薬局」と「調剤薬局」の2種類があります。
前者の薬局は、薬剤師が常駐して一般的な薬の調剤などを行う場所です。対して後者の調剤薬局には保険薬剤師が常駐し、保健医療で交付された処方箋に応じて保険調剤を行うという違いがあります。
また、調剤薬局は業態によって「点分業」と「面分業」の2つに分けられます。
| 点分業 | 医療機関の近くに配置されて、特定の医療機関の処方箋を主に対応する業態 |
|---|---|
| 面分業 | 不特定多数の医療機関の処方箋に対応する業態 |
点分業は門内薬局・門前薬局などが該当し、近接する病院の通院患者さんに利用されやすいことが特徴です。
一方で面分業は医療機関を限定せず、地域に根ざした「かかりつけ薬局」として幅広い患者さんの処方箋に対応します。
3.薬局経営についての現在の課題
薬局経営は薬剤師が年収1,000万円以上を目指せる方法であるものの、薬局を開業したからと言って必ずしも儲かるわけではありません。
儲からない薬局も多く存在するため、薬局開業の前に「儲からない理由は何か」を把握して対策しましょう。
以下では、現在の薬局経営に関する3つの課題を解説します。
3-1.薬価の引き下げがされている
調剤報酬や薬価は2年に1回のペースで改定されていて、薬価改定では基本的に薬価の引き下げが行われています。調剤報酬点数に含まれている薬剤料は薬価にもとづいて決まるため、薬価の引き下げは薬局の売上低下につながる問題です。
また近年の調剤報酬改定では、門前薬局などの「かかりつけ業務を行っていない保険薬局」の評価体系について見直しが行われています。
かかりつけ業務を一定以上行っていない保険薬局は調剤基本料の減額がされており、門前薬局の経営状態は厳しくなっていると言えるでしょう。
3-2.人材不足が続いている
薬局が応需する処方箋の枚数を増やしたり、経営する店舗を増やしたりするには薬剤師を雇用する必要があります。
しかし、薬剤師は人材不足が続いているため、薬剤師を雇用しようと思ったときにすぐ雇用できるとは限りません。
厚生労働省が公表する2024年12月分の一般職業紹介状況によると、パートを含む薬剤師の有効求人倍率は2.37倍でした。全職業の平均である1.22倍の2倍近い有効求人倍率からは、薬剤師が不足している状況が伺えます。
3-3.大手チェーン・ドラッグストアが競合として伸びている
薬局・調剤薬局の競合として、大手チェーン・ドラッグストアが伸びていることも調剤薬局の課題となっています。
経済産業省が公表する商業動態統計調査によると、ドラッグストアにおける調剤医薬品の販売額は下記の通りに増加していました。
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,524.6億円 | 5,954.98億円 | 6,291.66億円 | 7,192.48億円 | 7,955.19億円 | 8,713.58億円 |
また、日本チェーン・ドラッグストア協会によると、2023年度にはドラッグストアの全国総店舗数は2万3,000店を超えたとされています。
大手チェーン・ドラッグストアの増加は今後も続くと考えられ、薬局業界では調剤医薬品の販売数が伸び悩む可能性があるでしょう。
4.調剤薬局の経営のために必要なスキル
調剤薬局経営者になるには、以下のような経営にかかわるスキルを身につける必要があります。
・従業員をまとめ上げるリーダーシップ
薬局経営者は会社のリーダーであり、従業員をまとめ上げるリーダーシップが必要です。自社のビジョン・経営方針を掲げて従業員全員を引っ張っていく行動力や、従業員との間に信頼関係を構築できる能力が求められます。
・経営上の問題を解決に導く問題解決能力
薬局経営では売上低下や患者さんからのクレーム、薬剤にかかわる法改正への対応など、さまざまな経営課題が起こり得ます。経営上の問題を解決に導く問題解決能力があれば、経営の安定化がしやすくなるでしょう。
・調剤報酬に関する知識
調剤報酬は2年ごとに改定されていて、薬局の売上にかかわる調剤報酬点数や評価体系の見直しが行われることがあります。薬局経営者が調剤報酬改定に対応した経営を行うには、調剤報酬に関する知識が欠かせません。
調剤薬局の経営を考えている方は、まずは紹介した3つのスキルを身につけることがおすすめです。
5.調剤薬局の経営に成功するポイント
薬局経営者は経営に必要なスキルを身につけるだけではなく、薬局の利益を増やす方法や経営戦略も知っておきましょう。
調剤薬局の経営に成功するために押さえたい6つのポイントを解説します。
5-1.処方箋の枚数を増やす
調剤薬局の経営を成功させるためには、処方箋の枚数を増やすことが重要です。調剤薬局の売上は保険調剤が大部分を占めると言われており、医療機関の処方箋をどれだけ多く応需できるかが売上を左右します。
処方箋の枚数を増やすには、下記のような方法があります。
- 既存顧客のリピート率を上げる
- 脱落顧客を減らす
- 新規顧客を獲得する
既存顧客も新規顧客も処方箋の枚数は同じ1枚であるため、自局での購入経験を持つ既存顧客にアプローチしたほうが効率よく処方箋の枚数を増やせます。
さらに新規顧客の獲得もできれば処方箋の枚数は一層多くなり、売上向上を実現しやすくなるでしょう。
5-2.地域のニーズに応じたマーケティングを行う
調剤薬局はかかりつけ薬局としての役割を求められるようになっていて、地域との関係構築が重要性を増しています。地域の方からの認知度や来局頻度を高めるために、地域のニーズに応じたマーケティングを行いましょう。
例としては、地域のイベントに参加して医薬品の利用に関する相談会を行う方法があります。自局を利用するユーザー層を分析した上で、ユーザーニーズが高いOTC医薬品やサプリメント・健康食品などの商品販売を強化することも有効です。
マーケティングをしっかりと行えば既存顧客のリピート率が向上し、普段は薬局をあまり利用しない若者層など新規顧客の獲得も見込めます。
5-3.医療・介護施設と患者の双方へ営業活動を行う
調剤薬局が利益を増やすためには、医療機関・介護施設といった処方箋を発行する施設側と、処方箋を持ち込む患者側の双方に営業活動を行いましょう。
具体的な営業活動としては、下記のような内容が挙げられます。
| 医療・介護施設側への営業活動 |
|
|---|---|
| 患者側への営業活動 |
|
医療・介護施設と患者のどちらに対しても、営業活動では他との差別化ができる自局の強みを伝えることが大切です。「薬剤師の在宅訪問を行っている」「電子処方箋に対応している」といった強みを伝えられれば、処方箋枚数や来局頻度の向上が期待できます。
5-4.加算を漏れなく算定する
調剤報酬点数は大きく分けて下記の4項目で構成されていて、4項目の下にはさらに細かな評価項目が存在します。各評価項目は特定の要件を満たした場合に報酬点数が加算されて、請求する料金が決まる仕組みです。
- 調剤技術料
- 薬学管理料
- 薬剤料
- 特定保険医療材料料
しかし、加算の要件を満たしていても、算定していなくては請求できません。加算を漏れなく算定することで、売上向上につなげられます。
特に近年は対人業務の重要性が評価されており、薬学管理料を構成する「調剤管理料」の点数が高くなっています。ほかにも「地域支援体制加算」「後発医薬品調剤体制加算」など、対象の業務を行っている場合には加算を忘れないようにしましょう。
5-5.薬価差益を最大化する
薬価差益とは、薬の仕入れ価格と販売価格の差額によって生じる利益のことです。薬価差益を最大化することで、調剤薬局の利益を増やせる可能性があります。
そもそも薬の販売価格は、厚生労働省が「薬価」として公定価格を設定しており、薬局が自由に価格を決められません。
一方で薬の仕入れ価格は医薬品卸会社との交渉によって決まるため、下記のような方法で価格を引き下げる余地があります。
- 仕入れ価格の交渉をしてくれる共同購入グループに参加する
- 複数の薬局とボランタリーチェーンを構築し、薬の大量仕入れを行う
薬価の引き下げによって薬価差益は減少しているものの、利益率を高めるためにも薬価差益の最大化を見逃さないようにしましょう。
5-6.経費や人件費を抑制する
調剤薬局の利益を増やすためには、売上から差し引く経費や人件費を抑制することも重要です。
特に医薬品購入費は経費の大部分を占めていると言われており、経費の抑制には医薬品購入費を抑える必要があります。共同購入グループへの参加や、ボランタリーチェーンの構築などを行うとよいでしょう。
また薬局の人件費は薬剤師に支払う給与が大きいと言えます。人件費を抑制するには「薬剤師でなくてもできる仕事は調剤補助員に担当してもらう」「業務のデジタル化を進めて薬剤師の業務負担を減らす」などの取り組みが有効です。
6.今後調剤薬局を経営する上でやるべき施策
調剤報酬の改定などによって薬局経営を取り巻く環境は変化しています。調剤薬局の経営を成功させるためには、薬局に求められる役割に沿った施策を実施しましょう。
最後に、今後調剤薬局を経営する上でやるべき施策を5つ紹介します。
6-1.かかりつけ薬局・健康サポート薬局としての機能の強化
調剤薬局がかかりつけ薬局・健康サポート薬局としての機能を強化すれば、地域密着型の薬局として認知度向上や調剤報酬点数の増加を図れます。
かかりつけ薬局とは、患者さんが健康や薬のことを相談できる身近な薬局のことです。もう1つの健康サポート薬局は、かかりつけ薬局の機能に加えて、介護や食事などについても相談できる薬局を指します。
かかりつけ薬局・健康サポート薬局の機能を強化できる施策例をいくつか紹介します。
- 健康や介護に関する相談窓口の設置
- OTC医薬品や健康食品など物販の強化
- セルフメディケーションに対するサポートの提供
- 健康関連のイベント開催や、地域のイベントへの参加
など
薬局に求められるサービスは地域性による違いがあります。まずは地域の特性や患者さんのニーズを調べて、価値の高い施策を実施しましょう。
6-2.在宅医療・在宅介護への対応
国が整備を進める地域包括ケアシステムの中で、調剤薬局には在宅医療・在宅介護に対応できるサービスの提供が求められるようになっています。
調剤薬局が在宅医療・在宅介護に対応するには、下記のような施策が必要となるでしょう。
- 在宅訪問できる薬剤師の雇用、育成
- 医療機関や他調剤薬局との連携強化
- 患者さんの急変時への対応
- 在宅患者さんへの服薬指導などを常時行える体制の整備 など
また、在宅訪問を行う薬剤師が在宅業務を効率的に行えるよう、薬局DXの推進に取り組むことも重要です。
6-3.薬局DXの推進
薬局DXとは、デジタル技術の活用によって薬局の業務効率化をして、薬剤師が働きやすい環境を実現する取り組みです。
具体的には下記のようなデジタル技術が薬局DXのために導入・活用されています。
- 電子処方箋システムの導入
- 電子版お薬手帳の導入
- オンライン服薬指導の実施
- 薬歴管理などデータのクラウド管理 など
薬局DXを推進することで薬剤師不足を解消できるだけではなく、ヒューマンエラーを防止しやすくなって患者さんの安全性向上も図れます。
6-4.服薬情報の管理
2020年9月に施行された改正薬機法により、薬剤師が必要に応じて患者さんの薬剤使用状況の把握や服薬指導を行う「服薬フォローアップ」が義務化されました。今後の調剤薬局は、服薬情報の管理を徹底することが求められます。
服薬情報の管理では、調剤した薬剤の特性や併用禁忌といった薬学的な情報以外に、患者さんの年齢・BMI・既往歴などの情報も可能な限り収集しなければなりません。
また、患者さんの薬剤使用状況を把握するためには、薬剤師と患者が双方向でコミュニケーションを取れる手段を導入する必要があります。
6-5.医療機関との連携
改正薬機法では薬局の認定制度も新設され、特定の機能を持つ薬局は都道府県知事の認定を受けられるようになりました。患者さんが自分にとって適した機能のある薬局を選べるようにすることが認定制度の目的です。
薬局の認定制度には「地域連携薬局」「専門医療機関連携薬局」の2つがあります。
| 地域連携薬局 | 患者さんの入退院時や在宅医療などの際に、地域の医療機関や薬局と連携して対応できる機能がある薬局 |
|---|---|
| 専門医療機関連携薬局 | がんなどの専門的な薬学管理が必要となる患者さんに対し、専門医療機関などと連携して高度な薬学管理や調剤が行える薬局 |
調剤薬局が認定を受けることで、患者さんに適した調剤や薬学管理が行えるようになり、より地域に密着した薬局として認知度を高められます。
まとめ
薬局経営の収益性は、立地や処方箋枚数の多寡に加え、薬剤師の確保や調剤報酬改定への対応といった複数の要因によって大きく変わります。
もちろん、開業しただけでは必ずしも儲かる保証はありません。しかし、かかりつけ薬局や在宅医療に積極的に取り組み、地域のニーズに沿ったサービスを提供し続ければ、患者さんだけでなく医療機関からの評価も高まり、経営の安定化が見込めます。
また、薬局DXや服薬情報の管理による業務効率化も、薬剤師不足への対策と併せて重要となります。日々変化する薬価や法改正を見据えながら、柔軟に戦略を調整していくことが、今後の調剤薬局にとって不可欠な課題と言えるでしょう。